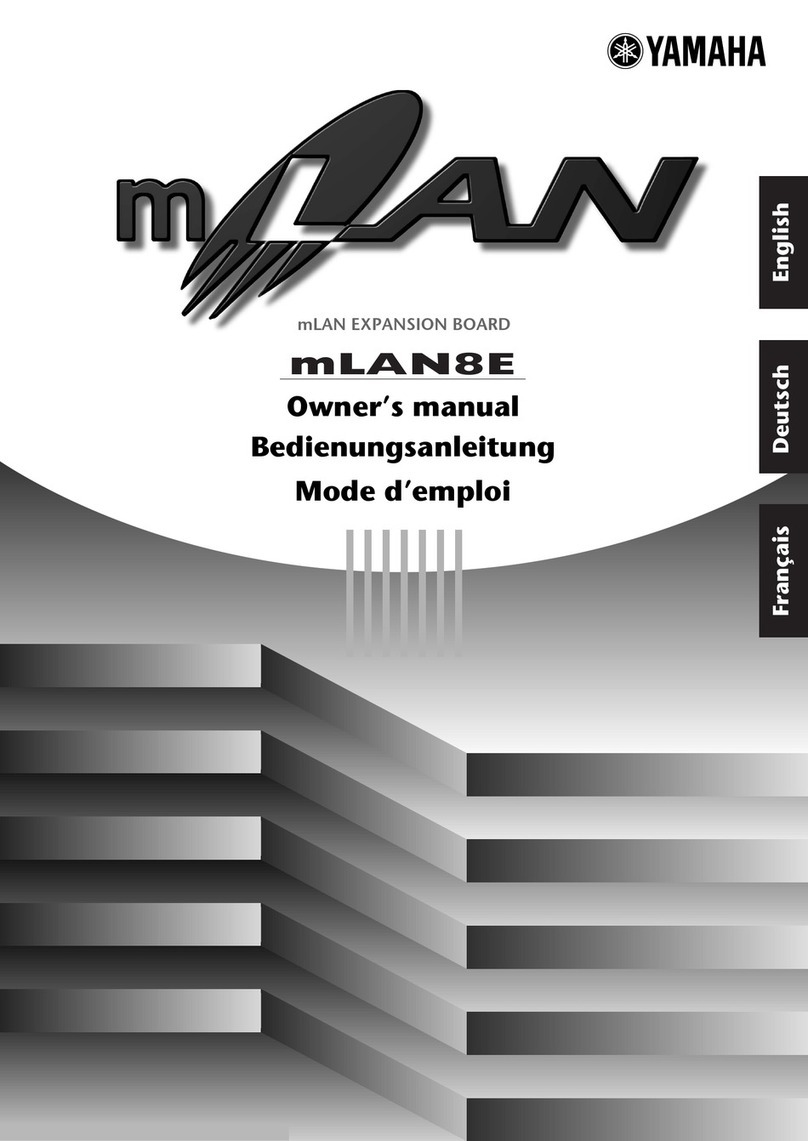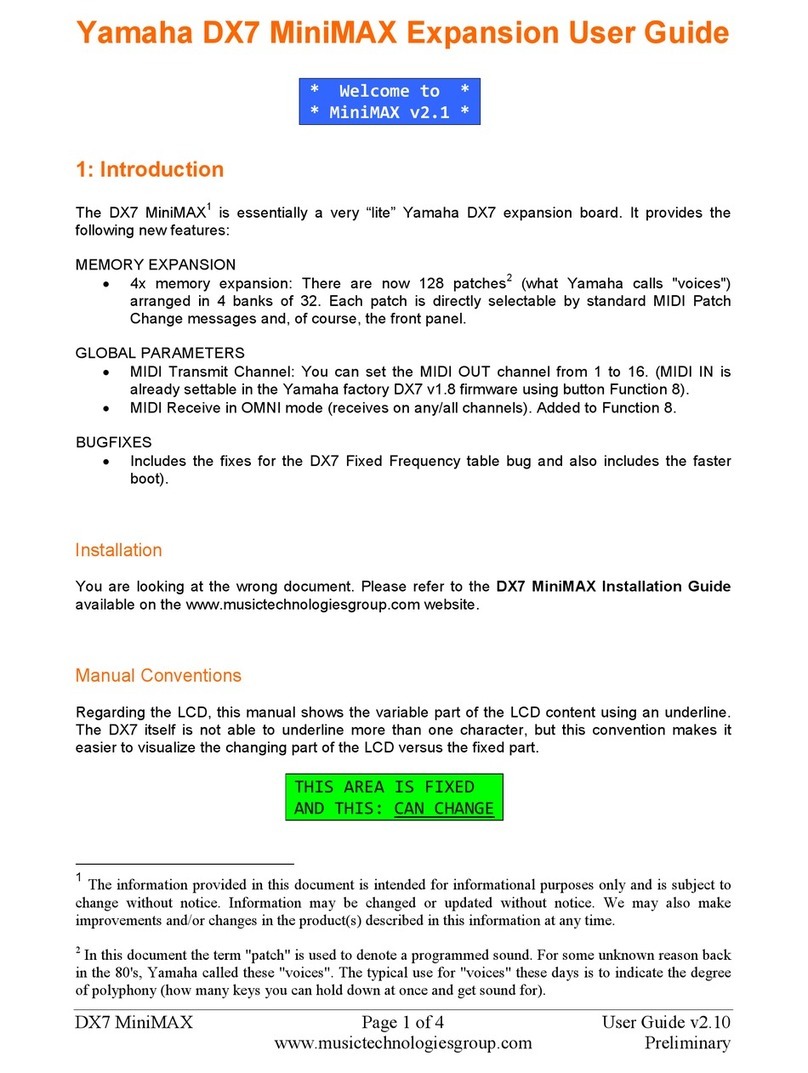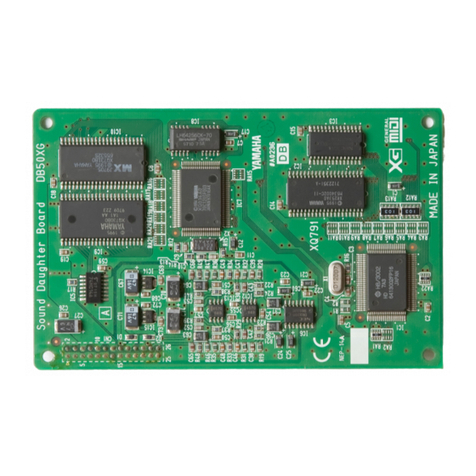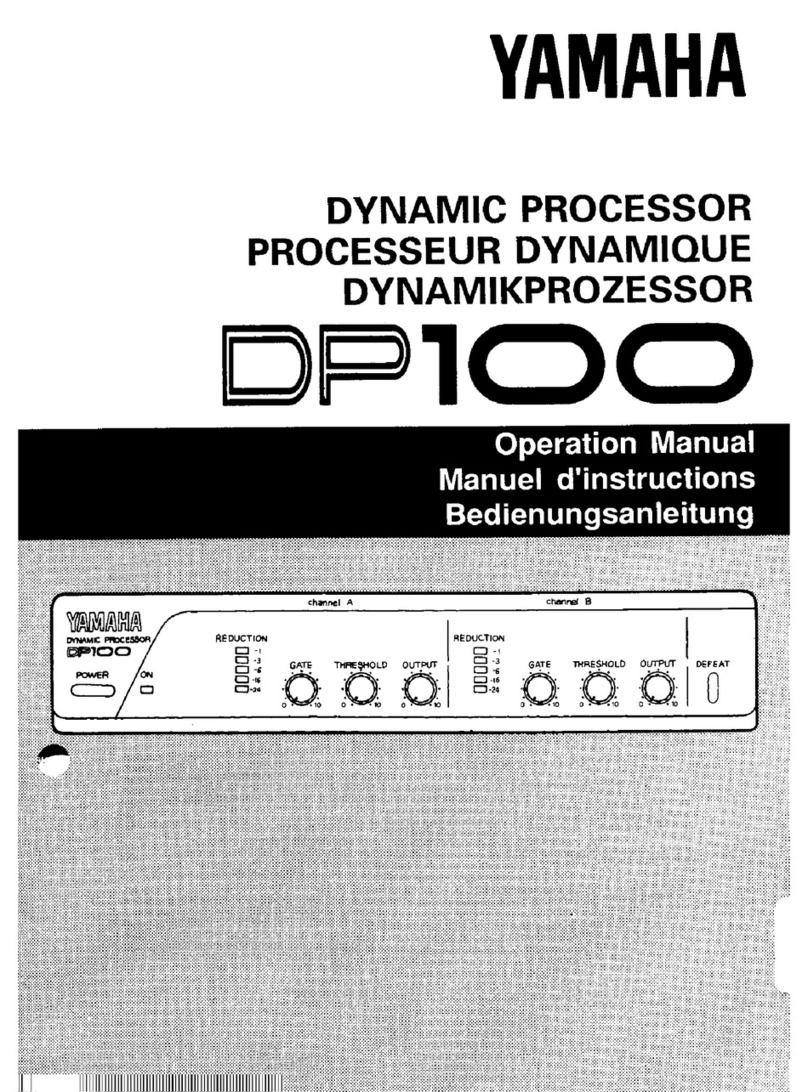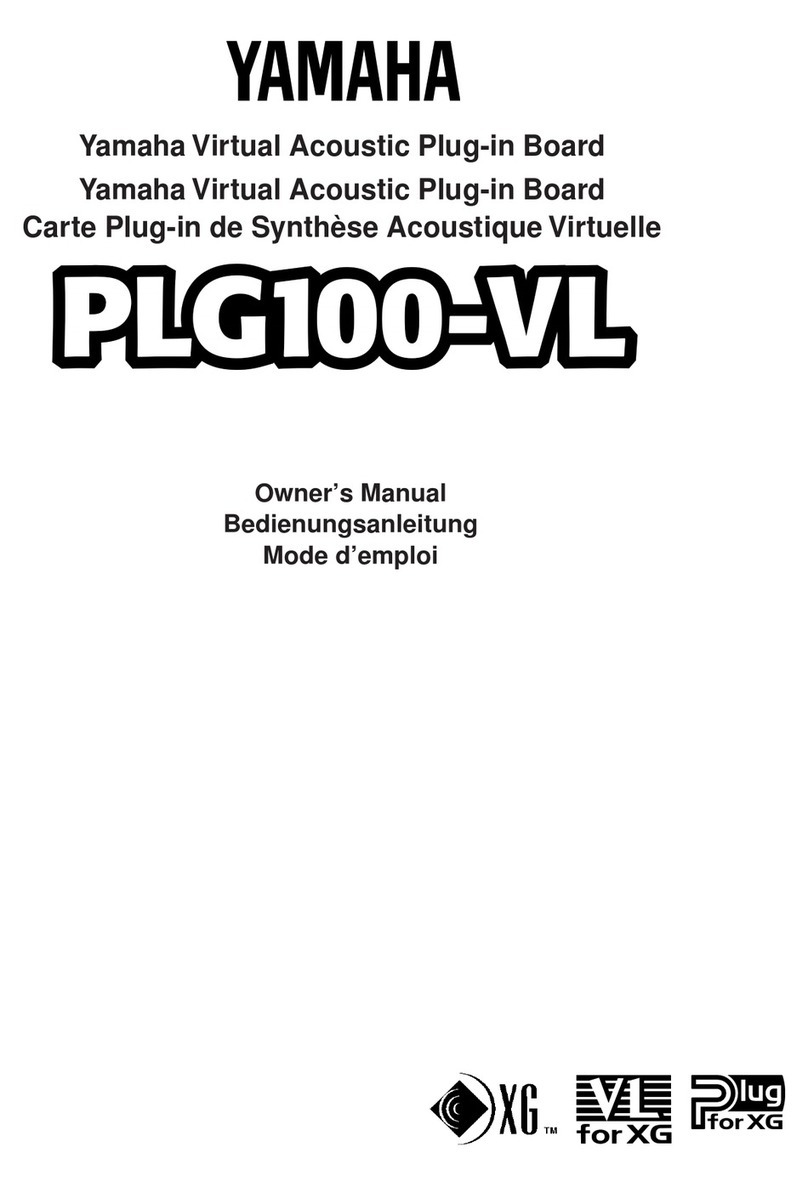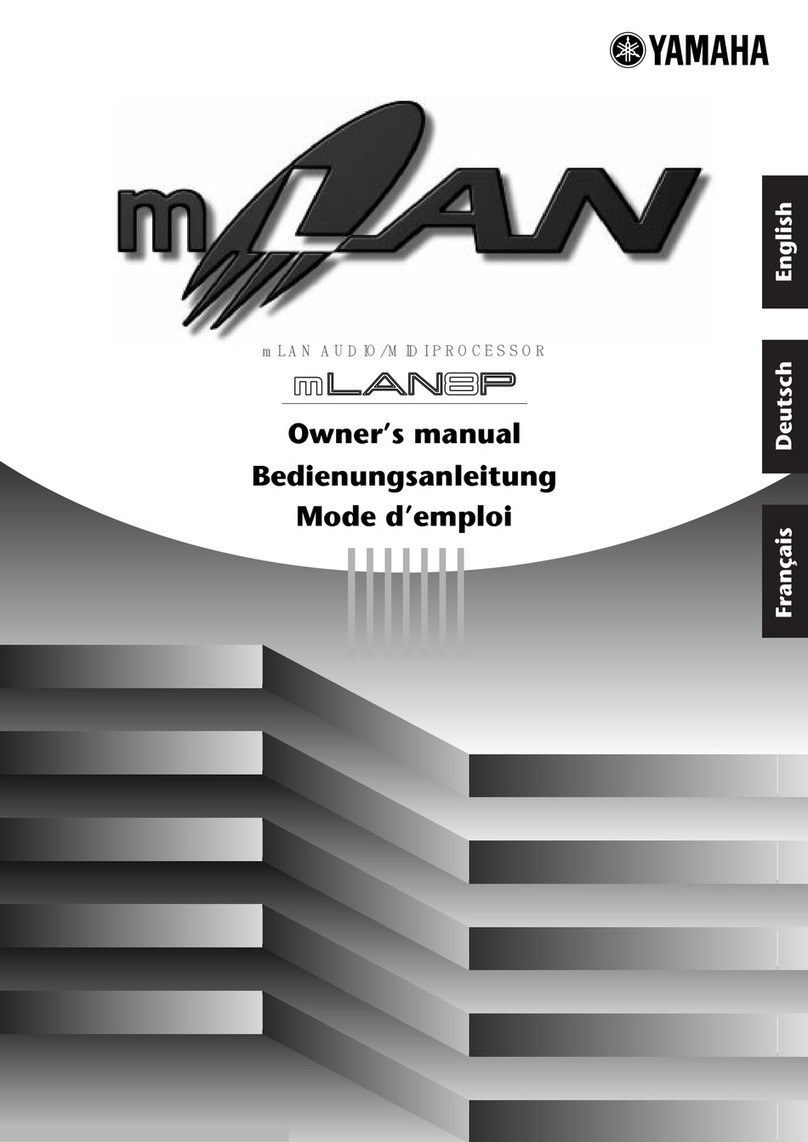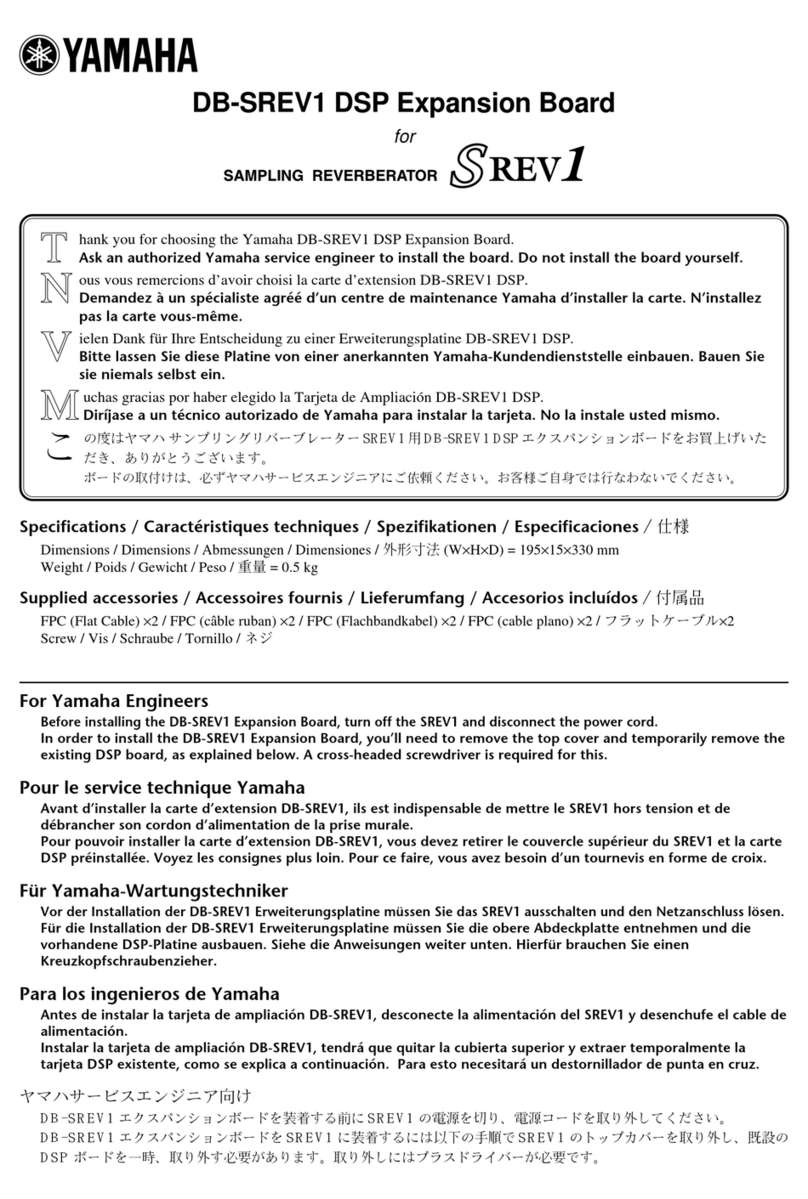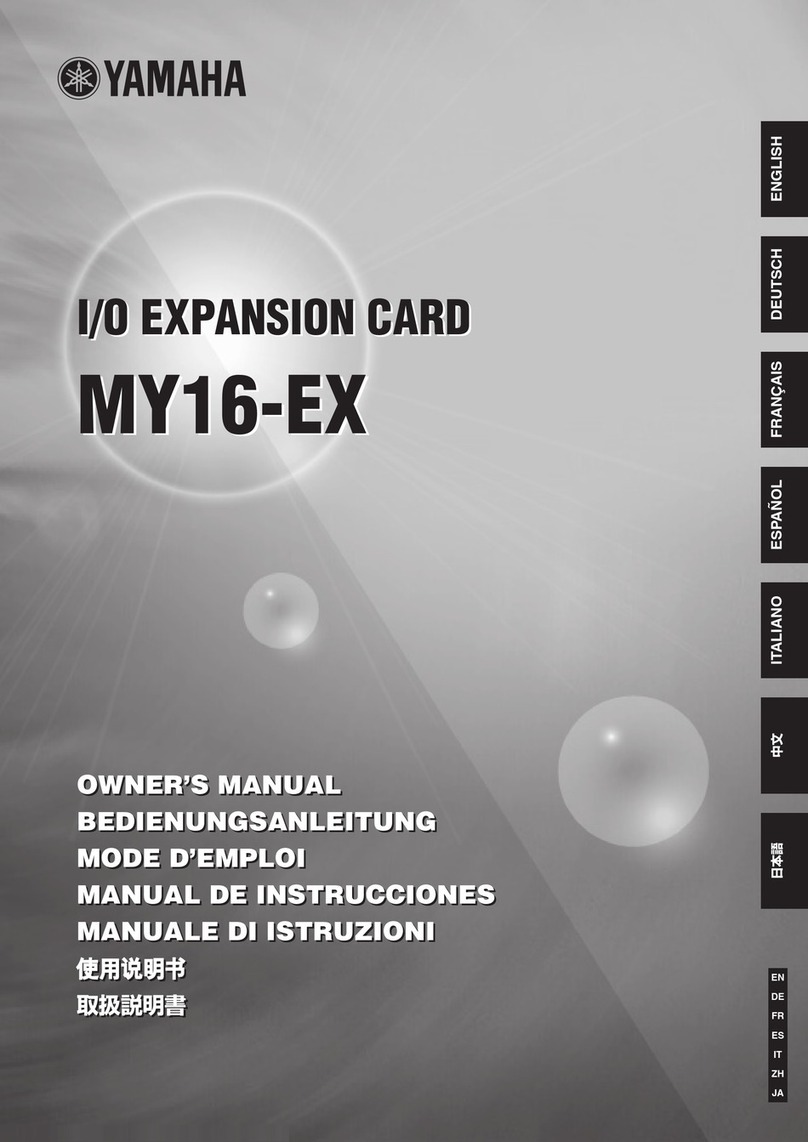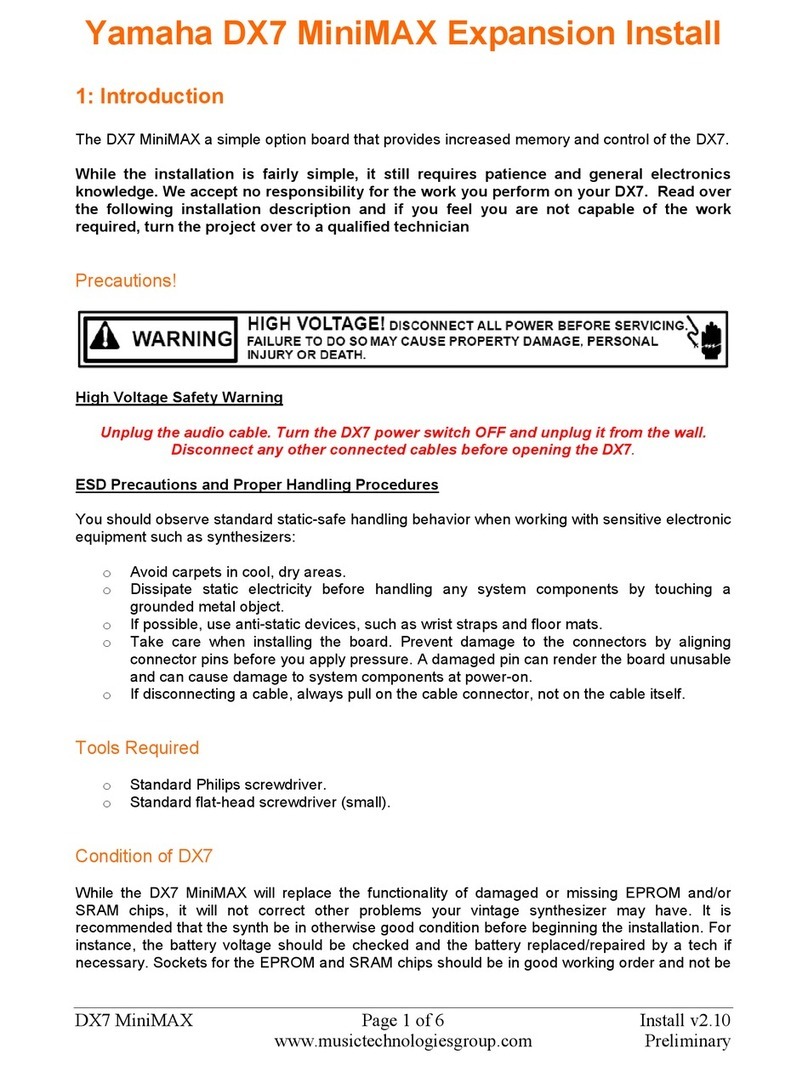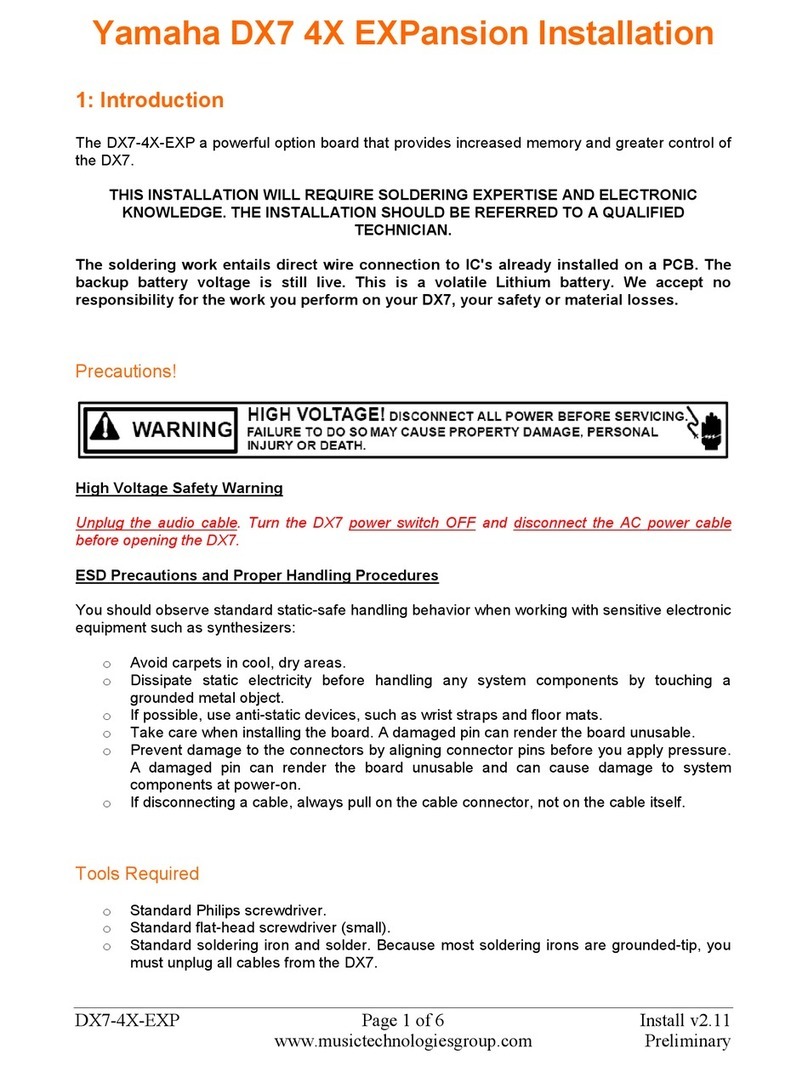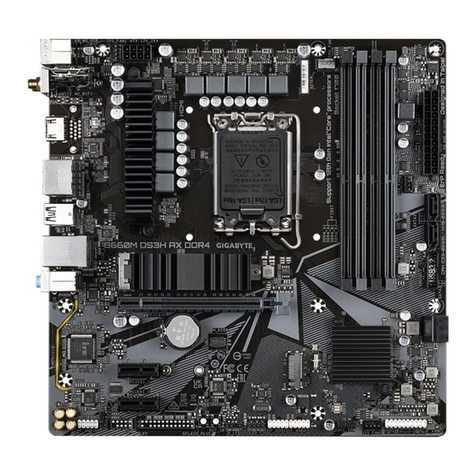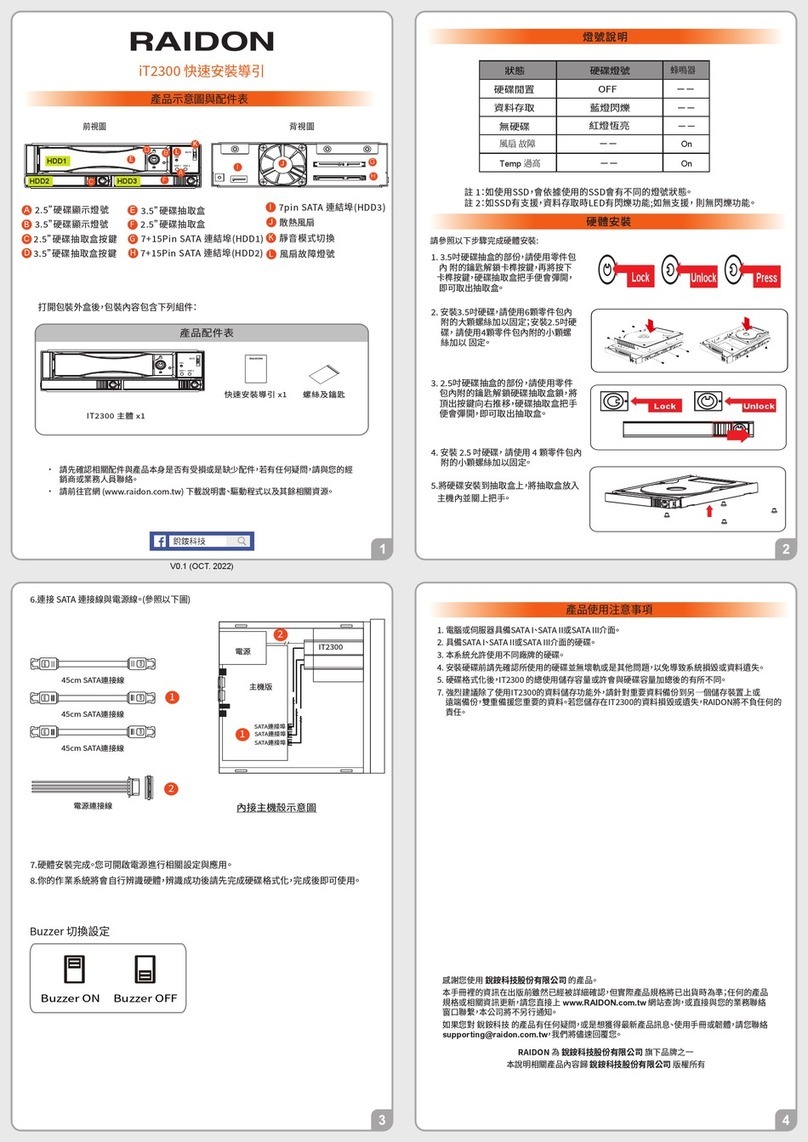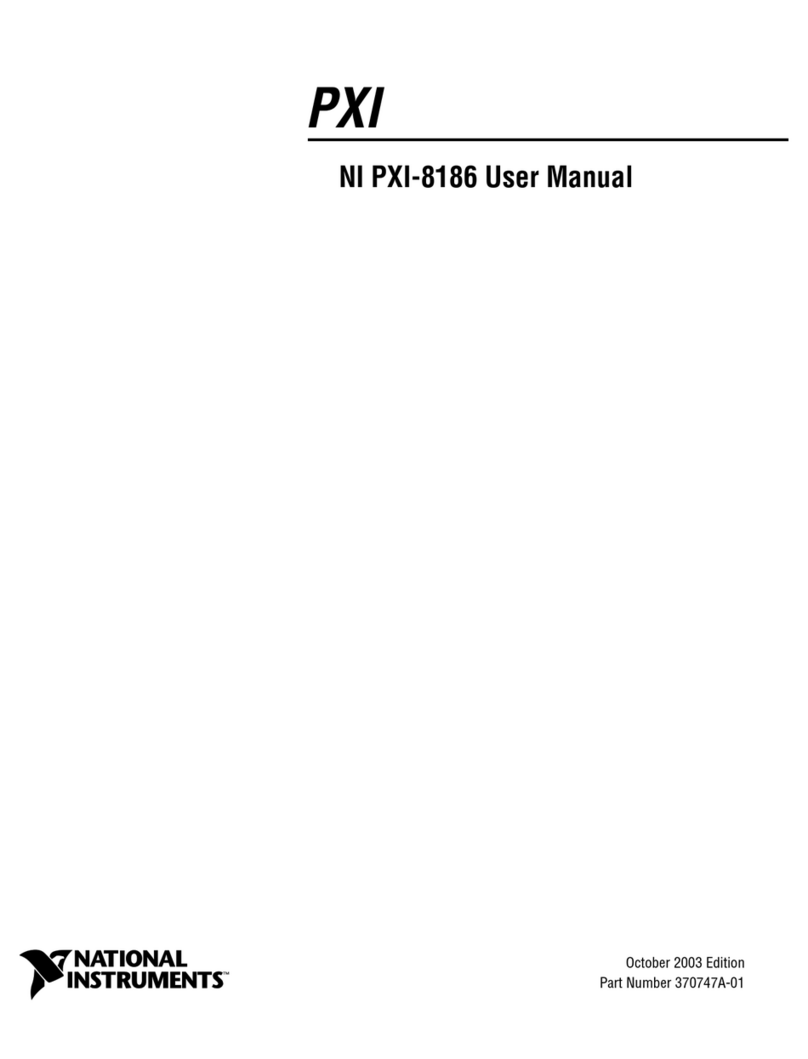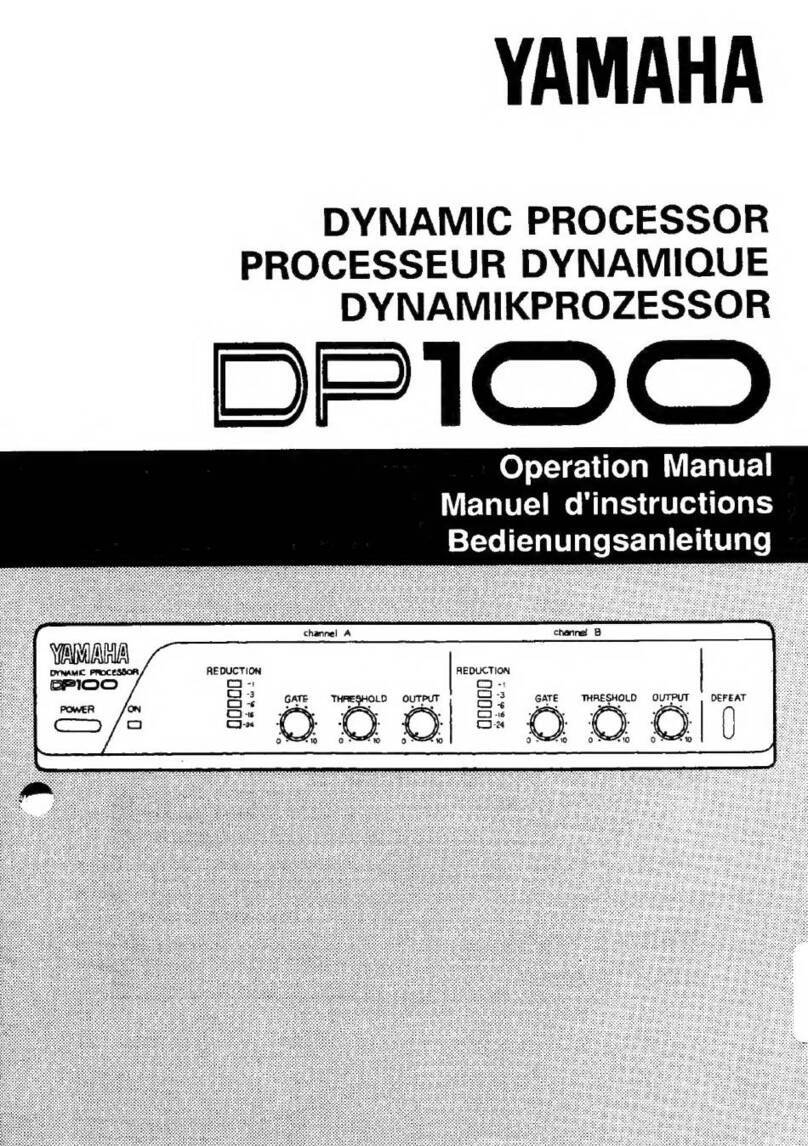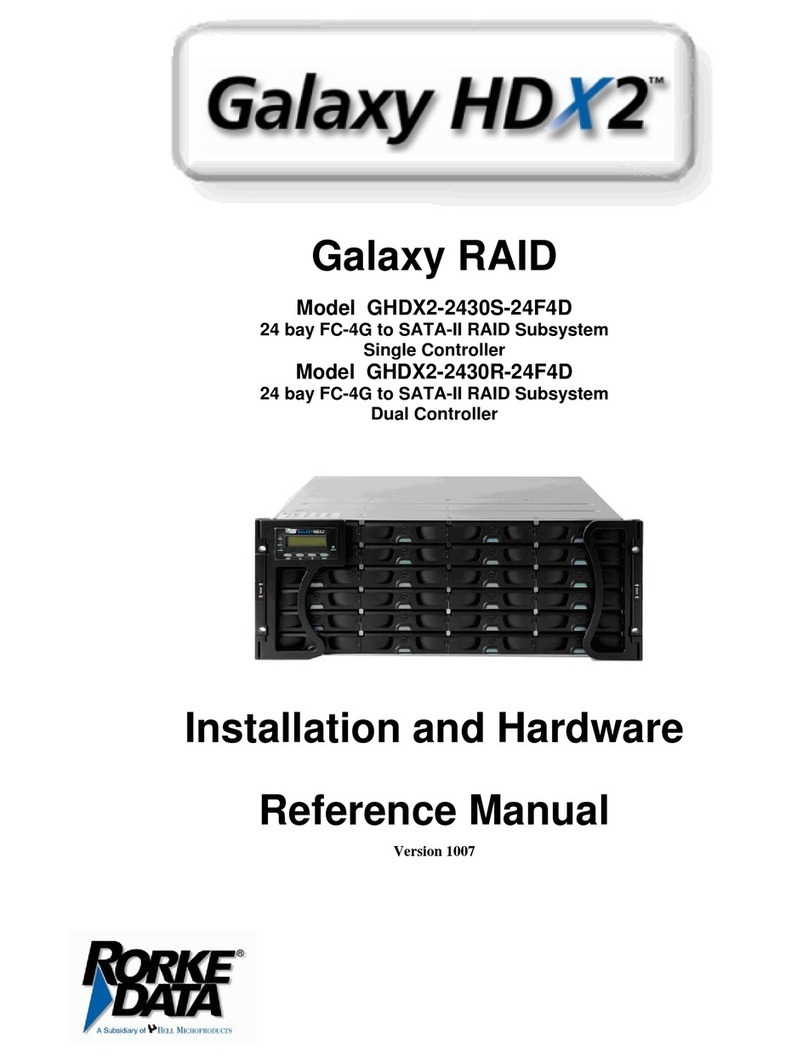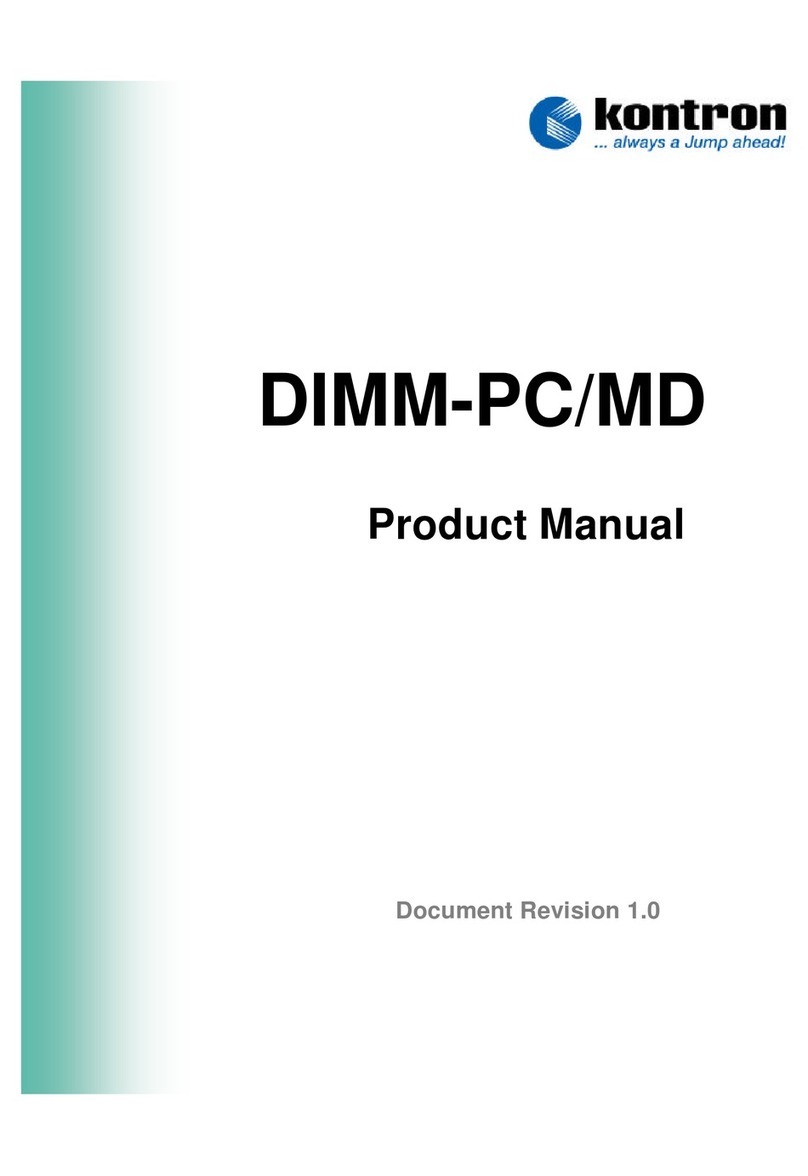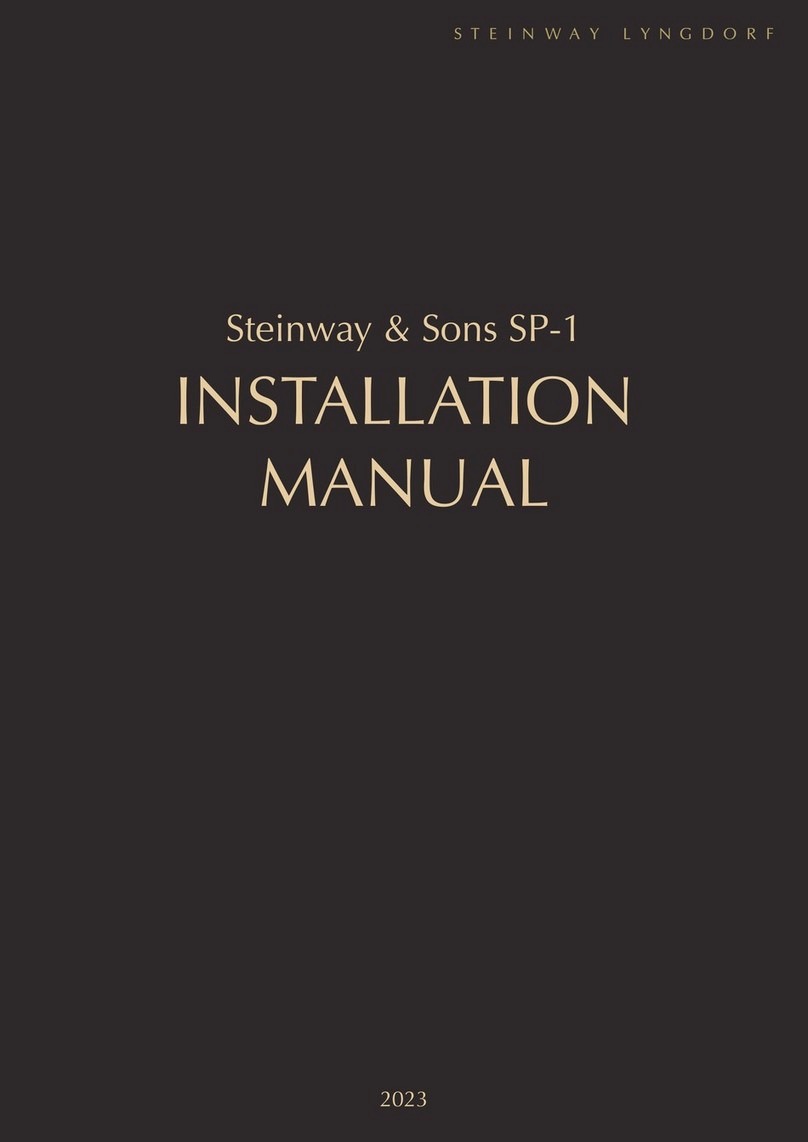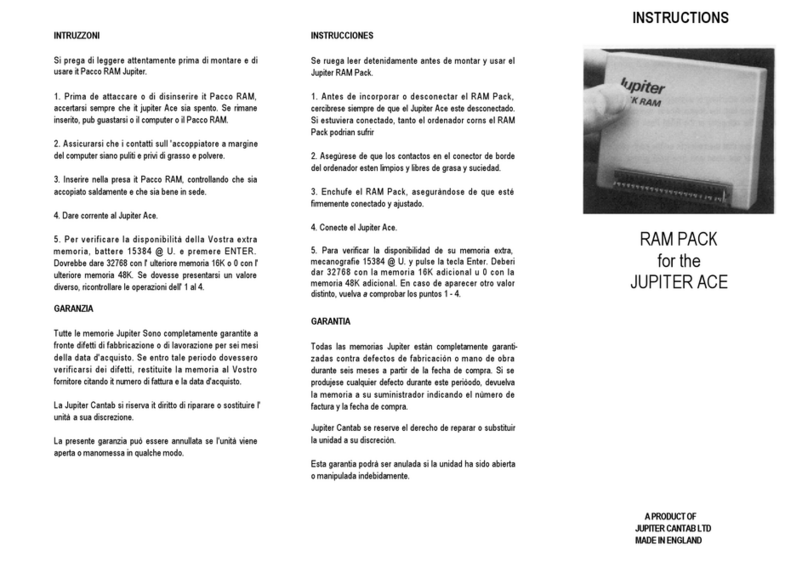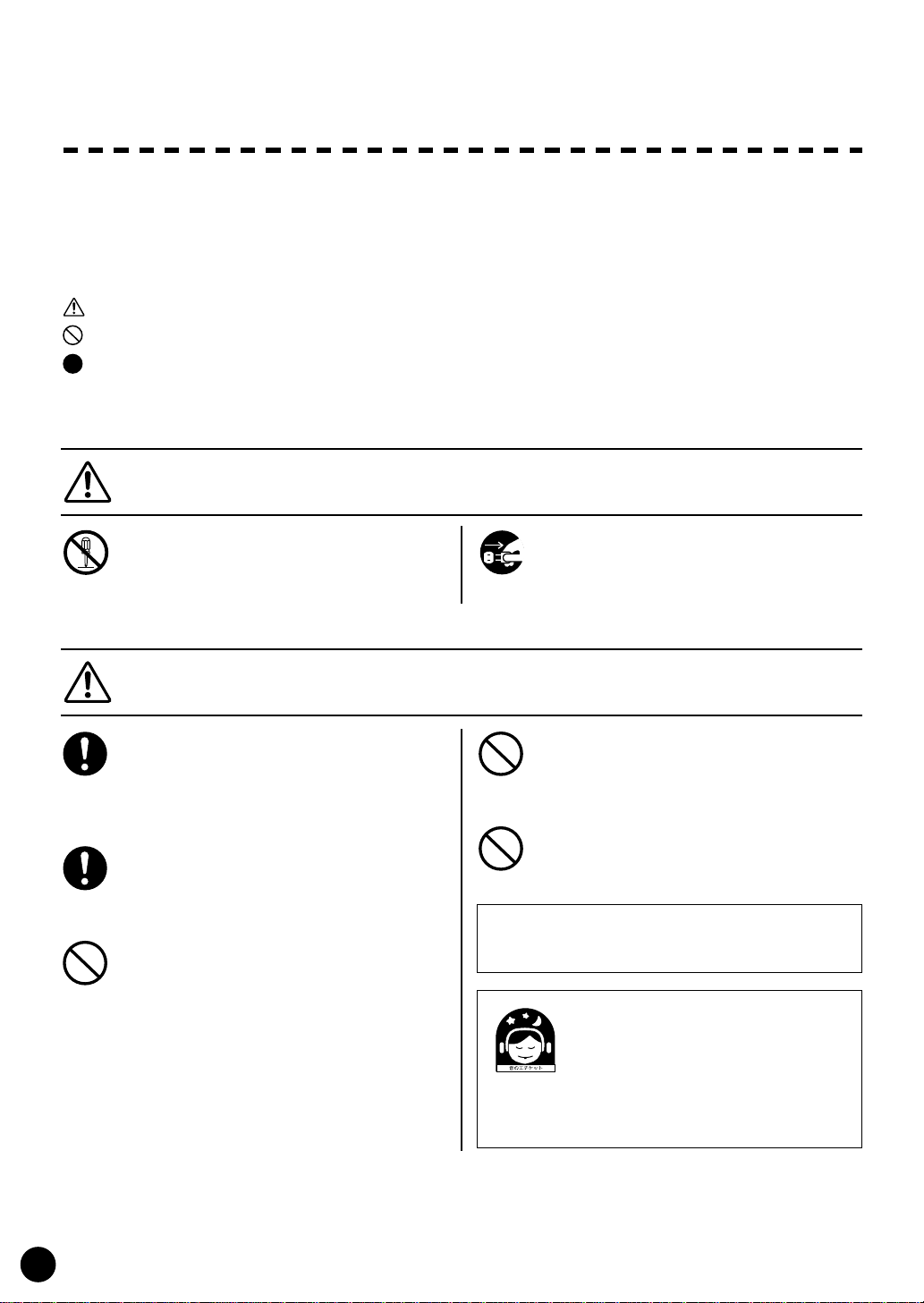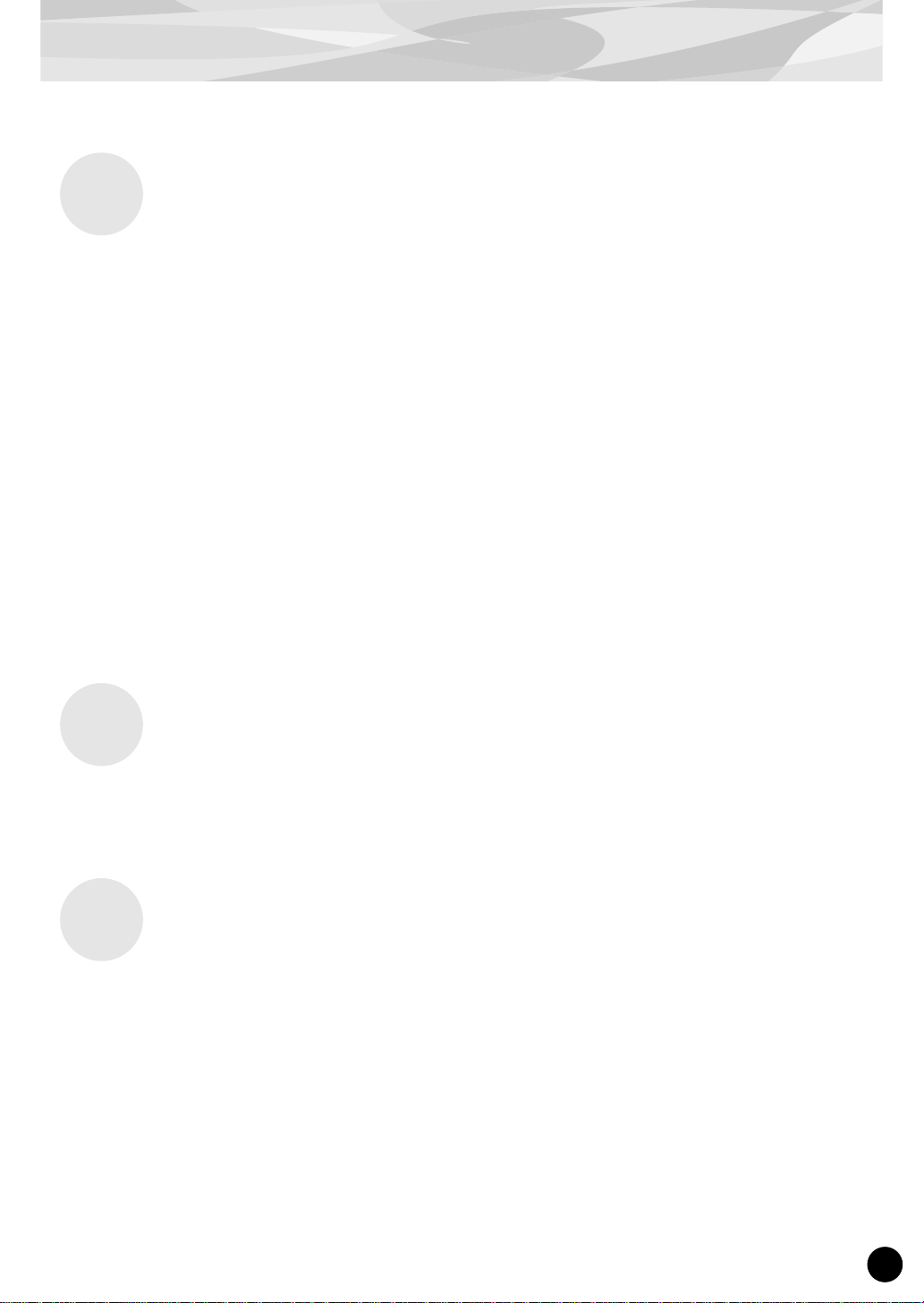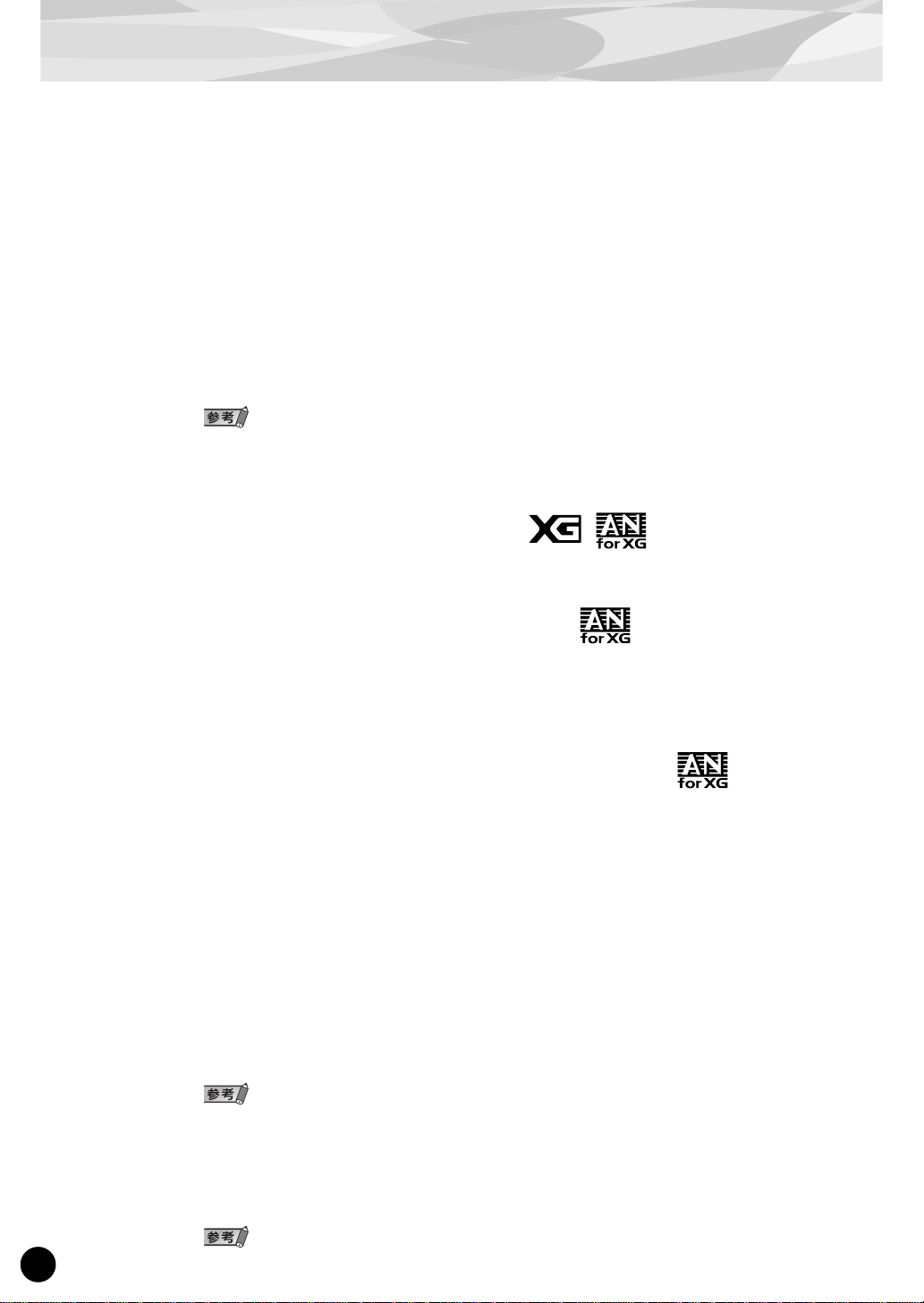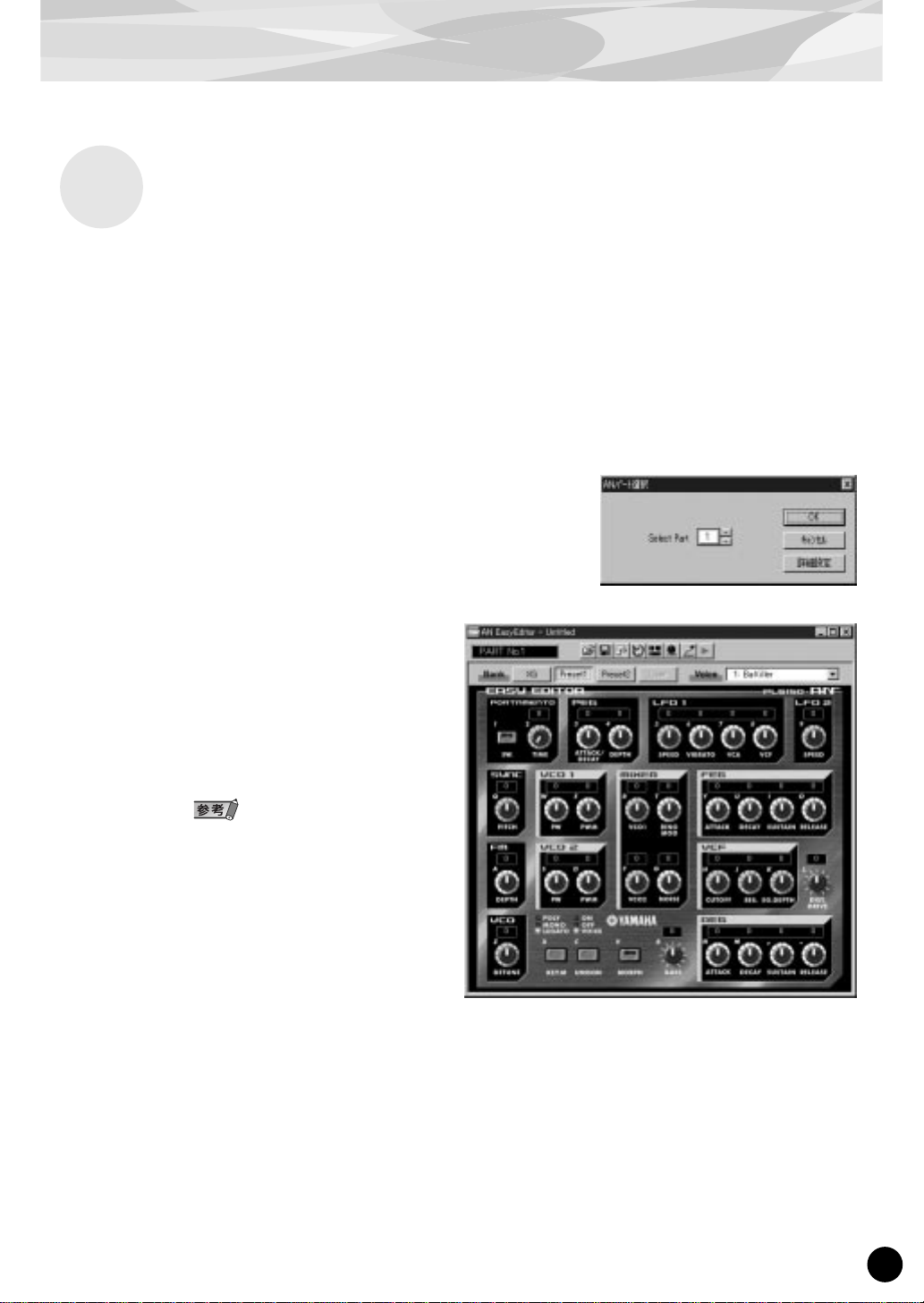4
もくじ
PLG150-ANについて........................................................................................................................ 5
PLG150-ANの特長 ..........................................................................................................................5
PLG150-ANの取り付け................................................................................................................... 5
同梱品................................................................................................................................................... 5
パッケージ以外に必要なもの ............................................................................................................ 6
仕様....................................................................................................................................................... 7
付属のフロッピーディスクについて.................................................................................................7
プラグインソフトウェアのインストールと起動(Windows98/95のみ)................................. 9
AN音源のしくみ....................................................................................................................................11
1. アナログフィジカルモデリング音源の構成 ..............................................................................11
2. AN音源のVCO … 音程と音色を決定する................................................................................12
3. その他のユニットによって音色を変える..................................................................................15
4. AN音源のVCF … フィルターにより音色を加工する/音色の時間的な変化をつける.........16
5. AN音源のVCA … 音量を調節する/音量の時間的変化をつける...........................................16
6. 音を時間的に変化させる … LFOや各種EGを効果的に使い分ける ......................................17
7. さらに音色を加工する … DistortionとEQ.............................................................................18
メモリーバッファー構成....................................................................................................................19
AN音色の選択(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).............................................19
ANネイティブパートパラメーターのエディット
(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).........................................................................20
ANネイティブシステムパラメーターのエディット
(モジュラーシンセシスプラグインシステムの場合).........................................................................21
AN音色の選択(XGプラグインシステムの場合)..............................................................................22
パート/パフォーマンスのレイヤーを指定する .............................................................................22
使用する音色を選ぶ..........................................................................................................................23
ANネイティブパートパラメーターのエディット(XGプラグインシステムの場合).......24
ANネイティブシステムパラメーターのエディット
(XGプラグインシステムの場合).........................................................................................................25
パラメーター詳細..................................................................................................................................26
PLG150-ANのネイティブパートパラメーター..........................................................................26
PLG150-ANのネイティブシステムパラメーター......................................................................32
資 料.........................................................................................................................................................35
ボイスリスト......................................................................................................................................35
シグナルフローチャート ..................................................................................................................48
アルペジオタイプリスト ..................................................................................................................49
コントロールマトリクス/フリー EGトラックパラメーターリスト............................................50
パラメーターネーム対応表 ..............................................................................................................51
MIDIデータフォーマット.................................................................................................................52
MIDIインプリメンテーションチャート..........................................................................................70
ソフトウェアのご使用条件 ..............................................................................................................72
ユーザーサポートサービスのご案内...............................................................................................73
保証とアフターサービス ..................................................................................................................75